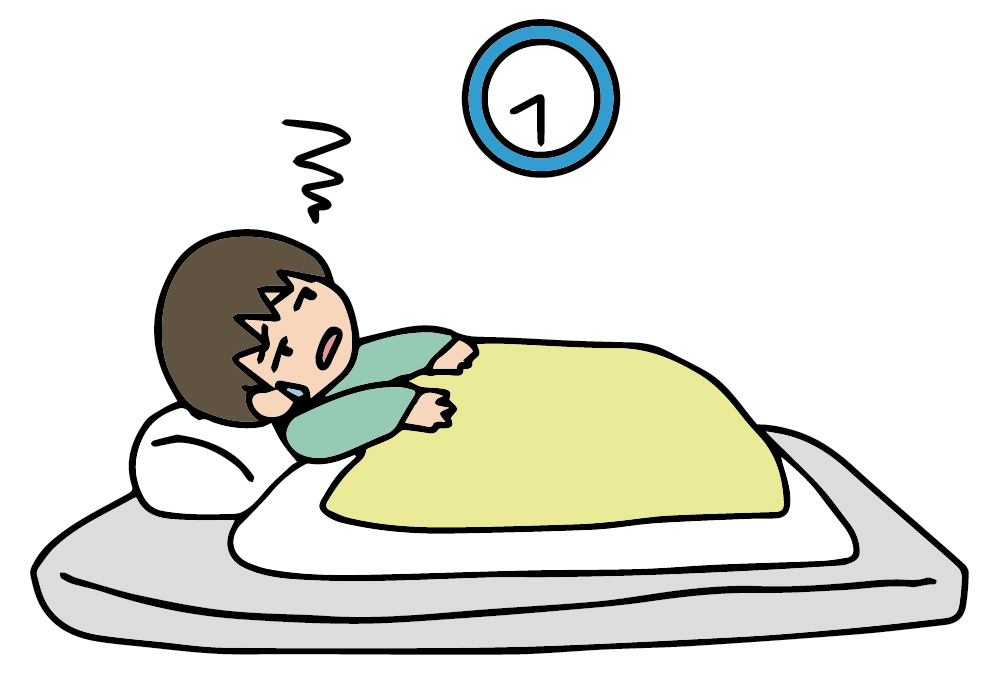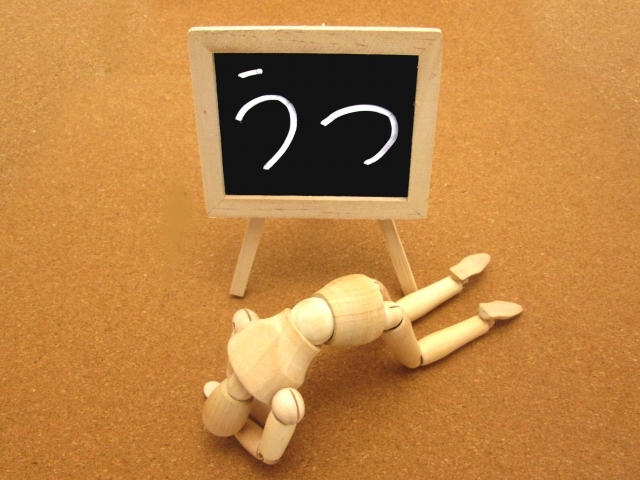ブログ

![]() 2016/01/07
2016/01/07
![]() コラム
コラム
トリガーポイント鍼治療がなぜ痛みに効果があるのか
トリガーポイント鍼治療がなぜ痛みに効果があるのか
トリガーポイントの説明をしようとすると、どうしても専門用語を使いたくなってしまいます。
しかし、それでは一般の患者さんには理解しにくいので、わかりやすいたとえや表現で説明することになります。
たとえば、こりの親玉みたいなものといったり、痛いと感じる所から離れた場所を押さえて痛むところとか。
でも今回は、あえて専門的な言葉を交えて痛みとトリガーポイントの関係を説明してみましょう。
【脱感作】とはどういうことなのか
花粉症などのアレルギー疾患の治療法の一つに【脱感作】という方法があります。

過敏性の原因となるアレルゲン、たとえばスギ花粉などをごく少量注射し、しだいにその量を増して過敏性を減弱させる方法です。
減感作療法といわれることもありますね。
一般には、生体に特定の抗原があり、同じ抗原が体内に入り再刺激に感じやすい状態にあることを感作されたといいます。
痛みの症状においても、この感作されたり脱感作されるという言葉が使われています。
もちろん、専門家のあいだだけの話しですが。。。
アレルギー疾患においての体内の抗原にあたるのがトリガーポイント
トリガーポイントが生じている状態が感作された状態です。
そして、トリガーポイントの部位を感作部位といいます。
ただ、トリガーポイントが生じただけでは、痛み症状が出るわけではありません。
感作部位が痛みの発痛部位という症状発現の構造に変化したときに痛みが発生します。
この時、その痛みの発生源のことを責任トリガーポイントといいます。
トリガーポイント鍼治療は、この痛みの発生源である責任トリガーポイントを探し出し、鍼で感作部位を刺激することで、脱感作を起こす治療法です。
脱感作されると、痛みの発生源は結果的に鎮痛されるわけです。
これがトリガーポイント鍼治療によって痛みがなくなるしくみです。
トリガーポイント治療が有効な場合とそうでない場合の違い
痛みの症状にトリガーポイント治療が有効ですが、そうでない場合があります。
有効な場合
- 進行中の傷害や炎症がないにもかかわらず、慢性的に持続する痛み
- 病院で診察を受けても、特別な異常所見が見つからない慢性痛
- レントゲンやMRIで骨格のすり減りや椎間板・半月板などの軟骨の異常が見られたが西洋医学的治療が効かない
無効な場合
- 急性期の椎間板ヘルニアなど組織の損傷がある痛み
- 明らかな炎症がある痛み
- 神経の損傷などによるしびれや感覚まひ
- 帯状疱疹ヘルペス後遺症のような神経そのものの痛み
- 心因性の痛み
痛み治療と予防にも有効なトリガーポイント鍼治療
痛みの症状はまだすべてが解明されているわけではありません。
しかし、筋肉や関節の動きに関して、なかなか良くならない痛みに対しては、トリガーポイント鍼治療が効果のある治療法です。
また、筋肉がしなやかで適度な緊張を保っていることは、痛み予防の決め手になります。
筋肉が硬いという状態は、いつ痛み症状が出ても不思議じゃないと思っていたほうがいいですね。
もし今痛みを感じていないとしても、トリガーポイント鍼治療を受けることで、感作部位(痛みのない状態のトリガーポイント)を治療することは予防につながるのですね。